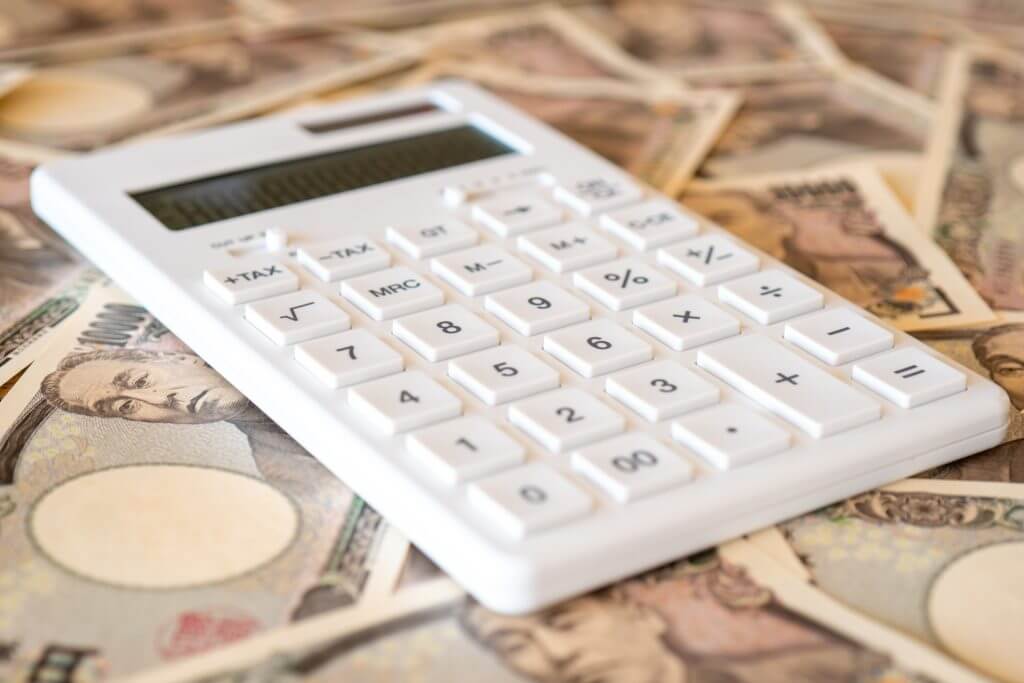
【採用担当者向け】採用コストの削減方法を紹介
「コストをかけても採用できない」「上から経費削減をするように言われている」など、人事担当者にとって採用コストに関する悩みは尽きません。
今回は、採用コストの平均額や、コストを抑えるための採用手法を詳しく解説します。
この記事の目次
一人当たりの採用コストの平均はどれくらい?
そもそも、採用コストの平均金額とその内訳は、どうなっているのでしょうか。
以下の表は、厚生労働省の調査による、採用方法別の平均採用コストの内訳一覧です。
| 応募方法 | 採用コスト(1件あたり) |
| 人材紹介会社 | 51.8 |
| ハローワーク | 1.9 |
| 委託募集 | 11.6 |
| 求人情報サイトへの掲載 | 29.6 |
| 求人情報誌への掲載 | 16.1 |
| 新聞広告への掲載 | 10.6 |
| 特別の法人等(地方公共団体、商工会議所、ナースセンター等) | 0.8 |
| 直接募集 | 7.3 |
| 縁故 | 2.4 |
| その他 | 3.2 |
※単位 万
※引用:「職業紹介事業に関するアンケート調査」(厚生労働省)
人材紹介エージェント経由での採用では1件あたり平均51万を超え、最も高い割合を占めています。さらに、調査対象の852事業所のうち100万以上かかったと答えた企業は全体の8%以上という結果でした。
ただし、職種や業種によって平均コストに差が出るので、あくまで目安として捉えましょう。
同調査によると、人材紹介サービスを利用する多くの企業で、「採用したい人物像に合った応募者を採用できるため」との回答でした。
有料の求人サイトは、掲載料がかかる先行投資型と、アクションが起こると費用が発生する成果報酬型の2つに大別されます。また、成果報酬型はさらに応募時点で費用が発生するタイプと、採用決定時に費用が発生するタイプに分かれます。
どのような求人サイトを利用するかによっても、かかるコストに差が出ているようです。
現在、新型コロナウィルスの影響で、採用市場全体は大きな転換期を迎えています。しかし、採用コストの削減は、依然として多くの企業の課題であることに変わりないでしょう。
そもそも採用コストは何を指している?
採用コストは大きく「外部コスト」と「内部コスト」の2種類に分けられます。ふたつのコストについて、詳しく確認しましょう。
外部へ支払う「外部コスト」
「外部コスト」とは社外に対して支払いが生じるコストで、以下のような費用を指します。
・求人掲載費
・人材紹介料
・会社説明会やセミナーなどの会場費
・採用パンフレットや採用動画の制作費
外部コストは、求人掲載費が占める割合が大きいという会社が多いのではないでしょうか。
成功報酬型ではない求人掲載は、応募がなければかけた費用が無駄になることもあります。だからといって安易に削減するのではなく、より効率的かつ効果的に掲載する方法を考える必要があるでしょう。
また近年は、採用活動で動画コンテンツを活用する企業が増えてきています。外部に動画制作を依頼する場合は、一定のコストを見込まないといけません。
採用活動で発生する「内部コスト」
「内部コスト」は社内で発生するコストで、以下のような費用を指します。
・人件費
・面接した応募者の交通費
・内定式や内定者懇親会の交際費
・リファラル採用のインセンティブ
・内定者の入社準備費用
内部コストは、人件費が大半を占めています。人事担当者が効率的に仕事を進めて、人件費を抑えることが採用コスト削減のカギとなるでしょう。
しかし、人件費は固定の給与として計上されているため、成果が把握しにくいという面があります。
また、説明会やインターンシップ、面接などにおいて人事担当者以外の社員の協力をあおぐこともあるでしょう。それらの人件費すべてを細かく計上して、正確な人件費を把握することは困難です。
内部コストは、実際の採用活動にかけた金額だけではなく、見えないところで多くの費用がかかっている可能性が高いといえます。
また、採用活動は実績につながらないことも多くあります。たとえば途中辞退、早期離職などが起きると、採用にかけた費用や時間は無駄になり、人事担当者の業務が増える要因です。
採用コストを見直す方法
採用コストが平均と比べて高すぎる場合や、しっかり採用コストをかけているはずなのに効果が現れない場合は、見直しが必要になります。
見直しを行うには、現状どのくらいの採用コストがかかっているか把握することが重要です。ここでは、採用コストを見直すための手順をふたつに分けて解説します。
現在の採用コスト全体を確認する
現在の採用コストを把握するには、採用コスト全体で考えるのではなく、前述した「外部コスト」「内部コスト」の項目で洗い出すと把握しやすいです。
内部コストであれば、求人掲載料、人材紹介料、外部コストであれば、人件費、応募者の交通費など、項目ごとに金額を出していきます。いつでも確認しやすいように、箇条書きではなく、表形式にすると良いでしょう。
項目ごとの金額を出したら、各項目を「外部コスト」と「内部コスト」の大枠に分け、それぞれどのくらいのコストがかかったかを把握します。
採用コストを精査して見直しポイントを探す
項目ごとの金額表を作成した次に行うのは、採用コストの精査です。金額だけを見るのではなく、費用対効果の低い項目がないかを確認し、見直せるポイントがないかチェックしていきます。
外部コストであれば、1人あたりの採用単価を算出するのが有効です。1人あたりの採用単価を出すには、まず外部コストを採用手法ごとに分けます。
さらに、各手法の応募者数、面接者数、内定者数、入社人数を計算しましょう。採用活動の最終的な結果は入社人数に表れるため、各手法の採用コストを入社人数で割って1人あたりの採用単価を出します。応募者数などは、どのくらいの宣伝効果があったかなどを見るときに有効です。
採用コストを削減するための8つの施策
採用コストを精査する方法について、項目を洗い出し、問題点を見つける方法までを解説してきました。さらに重要なのは、原因を把握し、どのようにしてコスト削減ができるか、解決策を出し実行していくことです。
ここでは、採用コスト削減につながる8つの施策を紹介します。
1.選考フローの見直しを行う
ひとつ目の施策は、選考フローの見直しです。無駄な工数を削るため、選考の流れを洗い出して、必要以上にかかっている工数はないか、必要のない業務がないかを見直します。
選考フローで見直すべき部分のひとつが面接業務です。たとえば、面接を複数回設定している会社や、面接の度に応募者に来社してもらう会社は、見直しの余地があります。
まずは会社の規模や業務の難易度に応じた面接数かどうかを考えてみましょう。
面接を複数回設定しているものの、採用要件や基準を明確にしておらず、形骸化しているケースや、応募者にとっての負担が増え、内定辞退につながっているケースもあります。
この場合は、面接のフローが現状にマッチせず採用コスト増につながっているため、改善が必要です。面接の回数を減らす、1次面接はオンラインで実施するなどの対策を講じなければなりません。
2.ミスマッチを防ぐ
早期離職は、求職者側の「思っていたのと違った」「期待されるスキルを有しておらず業務が厳しい」など、採用時のミスマッチが原因である場合が多いです。採用や教育にかけた労力が水の泡になれば、企業にとって大きな損害になります。
つまり、ミスマッチによる早期離職を減らすことが、コスト削減につながるといえるでしょう。
ミスマッチを防ぐためには、以下の3点が重要です。
・企業側が求める人物像を明確にし、それに沿った募集・選考を行うこと
・応募者がしっかり企業への理解を深め適性を考えていること
・応募者が判断しやすい正しい情報提供を企業側が行うこと
3.採用サイトを充実させる
コストを抑えながら、求めるターゲット層にマッチした人材を確保するには、自社の採用サイトの充実が不可欠です。理由は以下の3つがあげられます。
・自社サイトなら高額な掲載費が必要ない
・求職者が企業研究をしやすくなり、応募意欲につながる
・多くの情報を提供することで、ミスマッチを防ぐことができる
仕事内容はできるだけ詳しく紹介し、働くスタッフのインタビューや社内の雰囲気が分かる動画や画像も豊富に掲載すると良いでしょう。求職者はそれらの情報から自分がその会社で働く姿をイメージしやすくなり、モチベーションが高まります。
また、情報を多く提供することで、ミスマッチの原因になるような誤解や認識のズレが減るでしょう。
4.求人媒体を見直す
「有名だから」「いつも利用しているから」という理由だけで求人媒体を選択していませんか。
せっかくコストをかけて求人を出すのであれば、より効果的な媒体を選ぶことがコスト削減につながります。
ターゲット層に適した求人媒体を選択することで、効果が大きく変わります。継続的に効果測定を行い、職種や時期によって最適な求人媒体を見直しましょう。
また、IndeedやGoogleしごと検索などの求人検索エンジンは、無料で掲載することができます。
多くの求職者に見てもらえるように、継続的に無料の求人媒体を利用するのも良いでしょう。
5.リファラル採用を導入する
リファラル採用とは、自社の社員をとおして、社員の友人や知人を紹介してもらう採用手法のことです。
紹介してくれた社員にインセンティブを渡すこともありますが、リファラル採用であれば広告費が必要ないため、大きく採用コストを削減できます。
採用コストを抑えつつ人材を確保したいなら、リファラル採用とリファラル採用を促すための社内紹介制度の整備を検討してみると良いでしょう。
リファラル採用は、会社についてよく知っている社員を介して行われる採用であるため、ミスマッチが起こりにくいのが特徴です。また、人材の定着が見込めるため、新たな人材確保にかかる追加のコストも発生しにくいメリットがあります。
社員の離職に頭を悩ませている会社であれば、人材補充のための新たな採用コストの削減にもなります。
6.ダイレクトリクルーティングを導入する
企業側が、求職者に直接アプローチする攻めの採用手法を「ダイレクトリクルーティング」といいます。ダイレクトリクルーティングは、SNSや求人媒体のスカウト機能を活用して行うのが主流です。
ダイレクトリクルーティングを導入するメリットは、自社で求めている人材にピンポイントでアプローチできる点です。求職者は求人を探す際に、知っている企業の求人票だけを見たり、「良い求人があったら」と考えたりする人も多く、求人広告ではそのような潜在層へアプローチすることができません。
その点、応募を待つ姿勢ではなく、企業側から求職者に働きかけを行うため、潜在層も含めて自社にマッチした人材に接触するきっかけをつくることができます。
また、ダイレクトリクルーティングがうまくいけば、費用対効果の低い求人媒体を利用しなくても済むようになるでしょう。外部コストにあたる、求人広告掲載料の削減が可能です。
ただし、他社サービスが提供している人材データベースを活用する際には料金が発生することもあるため、利用前にはきちんと比較をしておきましょう。
求人広告費に多大なコストをかけても採用につながらず、費用対効果が良くない場合は、ダイレクトリクルーティングを検討することをおすすめします。
7.助成金制度を活用する
助成金は、国や地方自治体が特定の事業者に対して行う給付のことをいいます。雇用促進や地域活性化などを目的に、国や自治体が雇用に関する助成金制度が設けられていることがあります。採用コストの見直しを行うなら、助成金の活用も視野に入れてみると良いでしょう。
助成金によって、直接的に採用コストが削減されるわけではありませんが、助成金で補てんすることにより、実質的に採用コストを減らす効果が期待できます。
ただし、助成金は従業員のいる事業者なら、必ずしも利用できるというわけではありません。助成金の種類ごとに受給条件が異なり、条件変更が行われることも多々あります。常に最新の助成金情報をチェックしながら、必要に応じた活用法を行いましょう。
8.採用代行を利用する
採用コスト削減の施策としては、採用業務を外部の採用代行(アウトソーシング)に一任する方法もあります。採用代行を利用するメリットは、採用活動がスムーズに進められることです。
ただし、採用代行の利用には一定の費用がかかります。自社の内部コストと比較して、採用代行の費用が下回るようであれば、採用コスト削減のために利用を検討すると良いでしょう。
なお、採用代行を活用する場合、自社で行える業務と委託する業務を分けて委任することも可能です。
内部コストが大きくかかっている部分があるなら、コストが多大にかかっている部分に注目して、一部を採用代行に委任しましょう。
採用コストを削減するならTalentClip
効率的な採用コストの削減を目指すなら、採用管理システムTalentClip(タレントクリップ)を活用してはいかがでしょうか。
TalentClipは、オールインワン型の採用管理システムです。自社の採用サイトの作成や、応募者管理の一元管理などの採用プロセスの管理を一括して行えます。これにより効率的な採用活動を実現できるので、採用コストの削減につながります。
また、IndeedやGoogleしごと検索といった求人媒体とも連携できるので、媒体ごとに何回も求人情報を入力する手間が省け、採用担当の負担軽減にも一役買ってくれます。
TalentClipについて詳しく知りたい方は、ぜひ一度お問い合わせください。
お問い合わせはこちら
まとめ
採用コストの削減は、求人掲載費用と人件費の削減がカギとなります。少しでも人事担当者の業務を軽減し、効率的な採用活動を行うためには、便利な採用管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。






